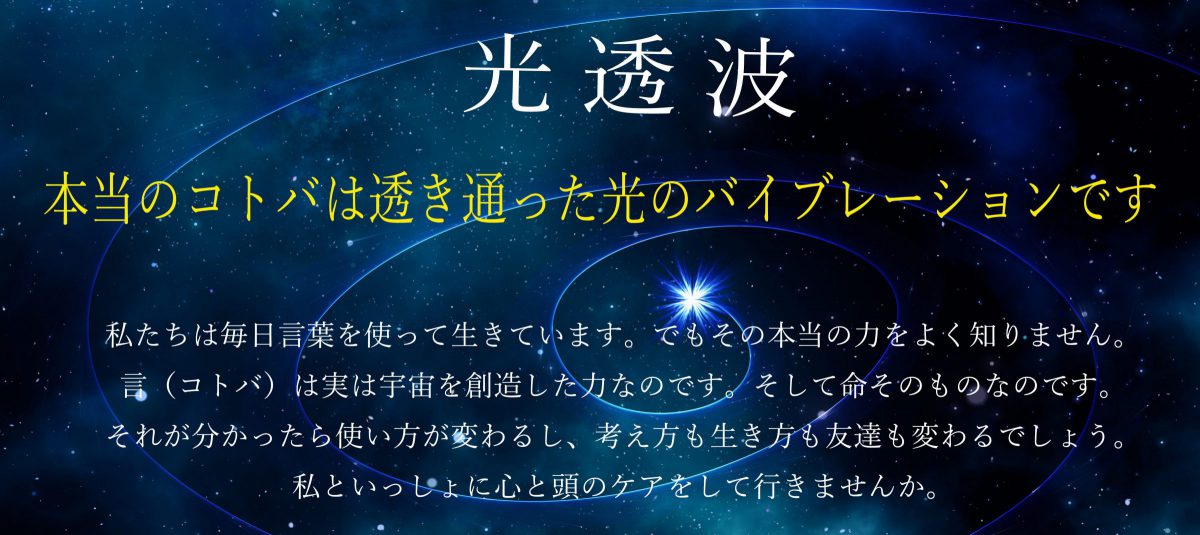以前勤めていた会社の上司のOさんは海外から帰国した私が日本社会に馴染めるように厳しくしかし温かく教育をしてくれました。その時の私の呼び名が「困ったさん」でした。
お辞儀の仕方、ミスをした時の謝り方、エレベータへの乗り込み方、何人かで歩く時の身の置き場、挨拶の仕方等、実に細かく丁寧に指導をしてくださいました。ユーモアのある方で、私が誰かにお辞儀をしているのを見て、
「君、腰が悪いの?」と訊くのです。
「はあ、若い時にぎっくり腰をしてから云々」とトンマな返事をし始めたのに対しては手を振って止めて、
「あのね、お辞儀をするときには体を二つに曲げるものなんだ。首だけコックリじゃだめ。頭を深くさげて、両手の平を膝につけて、ゆっくりと、一、二、三と数を数えるの。相手が誰かで数は変える。分かった?腰は治しなさいね」、という風でした。
かなり強く叱られたのは見積書の桁を間違った時です。通常かかる費用から計算して十分の一の金額で仕事を受けてしまったら会社は大損するわけです。しっかり意見されてから一緒に謝りに行ってくれましたが、担当者が変に思って稟議をあげていなかったので事なきを得ましたがこれは本当に落ち込みました。
「かわいい子には旅をさせろ」ということわざがあります。親元でぬくぬくと甘やかされて育つと世間に出てから通用しない人になるからあえて世間の波風にさらして子供を鍛えてもらうという意味だそうです。私の母は小さいときから私を他家に預けては何日も何週間もどこかへ行ってしまう人でした。まあ、それでも家にいる時には甘やかされていましたが。ともかく二十歳からよく海外へ一人旅をしました。二十歳後半からはアメリカで生活をしました。そして帰国後にOさんに出会った次第です。何をかくそうバイリンガルのお話の中に出てくるセミリンガルにより近い私でした。
私は生涯を通じて良い師に恵まれたと思います。小田野先生もそうでしたが良い師とは智恵と知識があるというだけではなく、愛がある人だと思います。今でもOさんを思い出す度に「困ったさん」という声音の中に込められている情愛を胸に沁みるように感じます。亡くなられて十年ほどになりますが、その人の愛は人の心にまだ生き続けているのです。まさに「愛は永遠なり」ですね。
情愛はエネルギーそのもので、強い伝播力を持っています。愛ある人の周囲には大勢の人が集まってきます。人は無意識のうちに自分にとって心地よいものをしっかり選び分けているのです。もちろん動物も、そして今は多くの人たちも認め始めていますが、植物さえも情愛に反応します。毎日大酒を飲む、覚せい剤を飲む、大食する、家事の手伝いを全く分担せず用事を頼むと怒って切れる、鬱になって引きこもる等の行為は情愛というエネルギー不足が原因です。こう言いますと、子供がこれらの行為をしている親御さんは怒るかもしれませんね。子供にはたっぷり愛を降り注いていると思って疑わないでしょうから。でもその愛にも種類があることを考えてみませんか。
 瀬戸内海に厳島という島があります。「イツクシマ」と読みます。大きな神社(神のやしろ)があり、世界遺産になっていますね。音が運んでいる他の文字でまず頭に浮かぶのが「慈しみ」です。厳しいのが慈しみと教えていただいていると受け止めています。厳しさが情愛なのかどうかの判別法のひとつは親が子供に対して、
瀬戸内海に厳島という島があります。「イツクシマ」と読みます。大きな神社(神のやしろ)があり、世界遺産になっていますね。音が運んでいる他の文字でまず頭に浮かぶのが「慈しみ」です。厳しいのが慈しみと教えていただいていると受け止めています。厳しさが情愛なのかどうかの判別法のひとつは親が子供に対して、
「怒る」のか「叱る」のかどちらなのかだと言えます。怒る場合は怒りという感情が混じっていますが、叱るのは諭すという行為です。諭すとは「目下の者(子供は目下)にことの道理を理解できるように言い聞かせる」という意味です。ことの道理を理解できるように言い聞かせるためにはカッカと頭に血が上って怒っている時にはできません。怒りという感情は主として大脳の偏桃体という感情のセンターが優位で活動している状態で起きています。「道理を理解させるために考える」時には前頭葉の前野が優位に活動しています。前頭前野と偏桃体の働きは拮抗します。つまりどちらか一方しか働かないという意味です。
怒っている時には叱れないのです
Oさんの諭しにこもっていた愛情は今でも私の胸を温かく潤しているのですから、子供にとって親に叱られた記憶は一生を通じて胸を温かく潤し、自己破壊的な行為をしないような歯止めになるのではないでしょうか。
2016.2.2 記