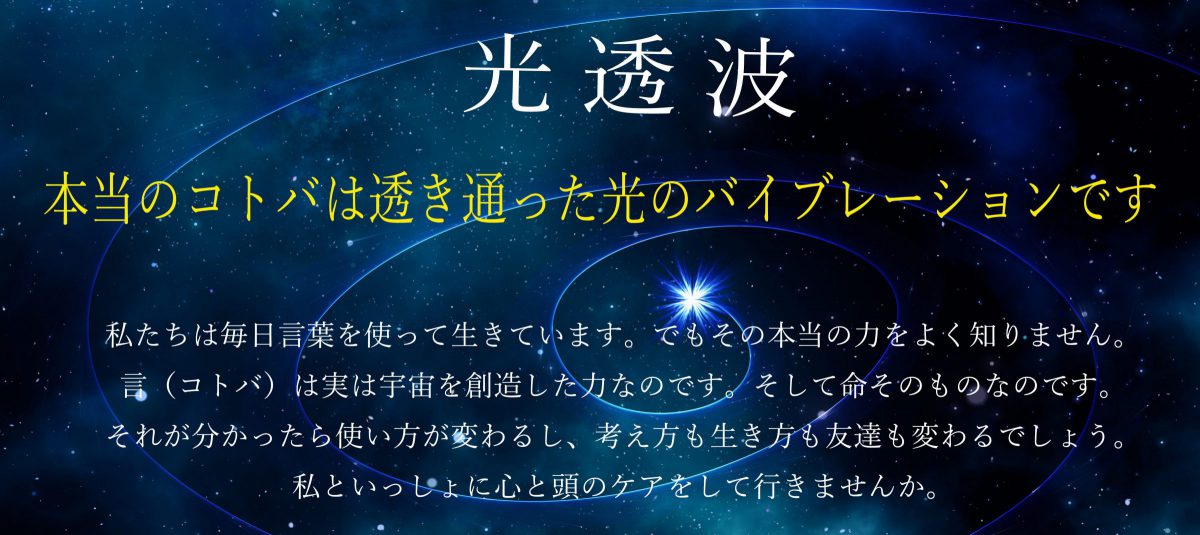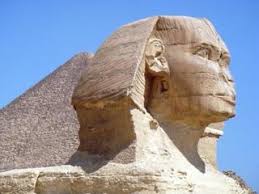一緒に暮らしていた家族が亡くなって約二年になります。亡くなる半年前くらいから庭仕事を少し手伝いうようになって、通算二年半、主に草取りをしました。
草を取りながら、その生命力に直に触れ、学んだことがあります。草は一応人間が「雑草」と分類したもので、きれいな花が咲く植物ではないものです。きれいな花が咲けば「園芸種」として販売され、珍重されます。それはさておき、雑草取りをしたことがある人ならすぐに分かることですが、「取っても取ってもすぐに又生えてくる」のです。とても良い環境とは思えないところにも生えるのです。もっと良い場所があるのに、踏み石の隙間の、狭くて、土の少ないところ、セメントの隙間などです。それを放っておくと石が持ち上がるほど大きく成長し、根がはって非常に取り除き難くなります。何という力強さでしょうか。
感心しながら根を残さないように気をつけてゆっくりと揺らしながら細かい根がつながっているものを抜くことに自己満足しながら、その反面、「何故こんなことをする必要があるのだろうか」とも思います。草は人間と共存できないのだろうか。考え出すと疑問は山のようにあることに気が付きます。
生態系全体の循環に関わる視点からなら、不要な草は無い筈ですが、「これが私の庭」という個人の所有地で、しかもあるガーデンデザインに沿って、要るもの、要らないものと分類すると、不要なものが雑草ということになります。人間社会はそうは行きませんよね。不要な人間は刑務所や精神病院、老人ホームなどに隔離しても、抜き取って捨ててしまうことはしません。ある意味では残酷なことかもしれません。自由を奪われて生きることを強制されているわけですから。草は自由に好きなところに生えます。それを私の勝手で、たい肥にして他の形で有効利用するなら草も役目を果たしているのだから抜き取っても良いと自分に言いながら抜きとります。
何故生え難いところにも生えるのか。「どこが良い場所、どこが悪い場所ということで決めていないのかもしれない」。要するに居心地だけで決めないらしい。では、何故か。一つには、居心地の悪いところを良い場所に変える結果を生むことです。自然界にとってセメントで固めた地面は異質な場所です。生命の育ち難い場所です。これを良い場所に変えるには、先ず生えることです。小さな草が根をはり、水を吸収し、土を集め、徐々に場所を広げ、石垣や舗装道路に亀裂を入れ、最後にそれらを崩し、ひっくり返し、粉みじんにして行きます。そうすると、あたり一面が草地になり、「居心地の良い」場に変わるのです。私の場合は「私の家」の敷地が崩れてしまうと困る事情があるので、対応策として雑草取りをしますが。
では誰がそれを指導指示しているのか。これは「自然」という文字を見ると分かります。
「自ずからに然らしめられている」という意味です。「そのような道理になっている」のに従って、大自然は運行しているのだと分かります。人間以外の生物の大多数、とりわけ植物と小さな生物である昆虫類や微生物には共通点があります。個体としてでなく、集団として共同作業をする点です。共同作業には全体を生かす為に常に個体が無料奉仕しています。個体は比較的には短命です。「生きているうちに成し遂げたいこと」などという時間的制限を持ちませんので、結果的には「倦まず弛まず」の作業ができます。何年かかろうと何十年かかろうとお構いなしに、次の世代が引き続き作業しますので、「人類滅亡後」何十年、何百年か経ると、地球上から人口の建造物は全部崩壊して無くなってしまいます。何千年も崩壊していないピラミッドやスフィンクスは人間が劣化を防ぐために補修をしているから保たれていますが、人間がいなくなればやはり、消えてしまいます。画像を見るとかなり劣化しているのが分かります。
草から学んだことは、当たり前のことが人間にとってはもはや当たり前でないことです。それは、
生物(人間もそうです)には自らの力で生きる能力が自然に備わっているという厳然たる事実です。これが多くの人間にはもうすでに当たり前ではなくなっているのです。自然から大きく離れた生活を始めてしまったからです。
何が自然で、何が不自然かという感覚の麻痺が起きてしまっていて、「あれ、何か変だ、怪しいぞ」と思わないで誰かに「これは良いものですよ」、「こうしないと死にますよ」などと押し付けられたり、脅かされたりすると言うなりになって、生殺与奪権を他者にゆずって、所謂「丸投げ」をして生きています。生きているとは言い難い状態ですが、ともかく脳死していないし、心臓が動いている限りは生きているとみなされます。でも自分で生きてはいないのです。
人としての役割は他の生物にはない能力を駆使して、大自然の営みを損なうことなくこの地上に生きる物全てと共存共栄し、更に他の生物には出来ないことを加えることで、天国のような美しい場所を作り、和気あいあいと交流して、互いの智慧を分かち合い、分かち合う喜びの音楽を奏でることだと思います。それを代弁している詩があり、初めてその歌を聴いた時に、私はそれに大きな感動と感銘を受けました。
天のお舟に乗り込んで つま弾く指を携えて
銀河に響くメロディーを 奏でるために旅立った
時代は来世 人々は 琴に玉水はじかせて
七色橋より滴り落ちる 光し羽衣、胸宿す
忘れ去られて那由他 不可思議 幾年過ぎた
物語を始めよう 再び始まる物語
お伽話とみまごうほどの美しき
天地をつなぐ物語 それはあなたの物語
余計かもしれない付け足し。
天界にいて光だったら体が無いので指は無い。つま弾けないとメロディーは銀河に響かせられない。琴(コト→言→光透)に玉水(玉のような音→母音・マントラ、美しい思いの響き)、虹のような美しい光の架け橋から舞い降りてくる光の羽衣を胸に宿す。羽衣は天に還る乗り物。この為に地上に降りて来たのに、人間として体を持ったが故に、すっかり奏でることを忘れて長い長い年月(那由多、不可思議は巨大数の単位)が経ってしまった。でも今からその物語を再び始めよう。
巨大数は面白いので抜粋して書いておきます。
一、十101、百102―――億108、兆1012、京1016―――那由他1060、不可思議1064、