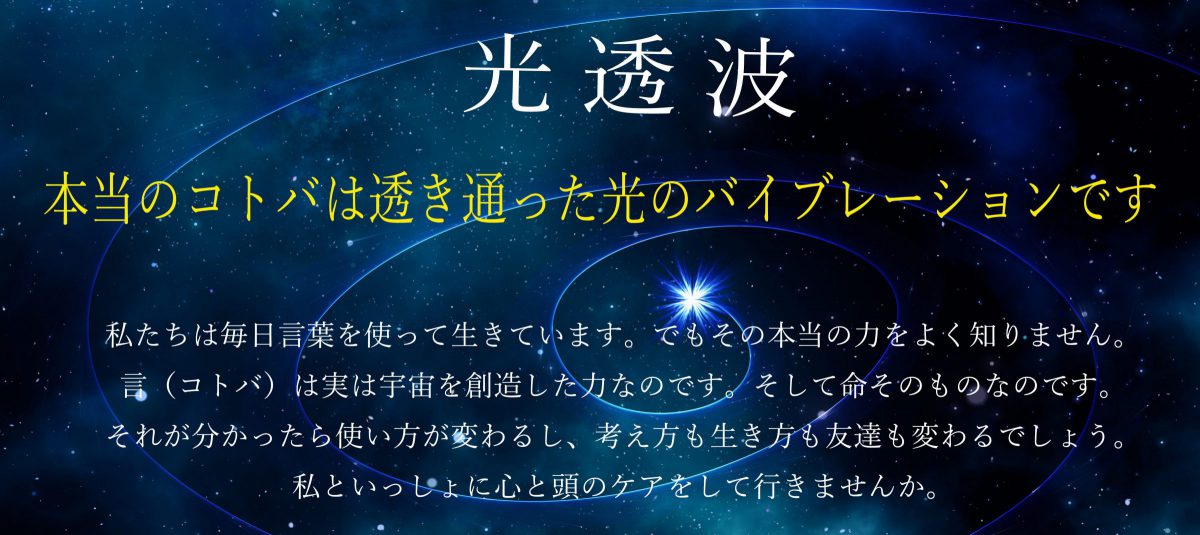新年のご挨拶文にありました、小田野先生が言われるところの「絶対の孤独」とはどういうものなのかを考えるに当たり、おそらくその意味での絶対性、あるいは唯一無二、というものを体験した人と言えるのではないかと思われるのが久司典夫さんです。スティーブ・アールさんの書かれた本に描写されていた久司典夫さんの体験を一例としてご紹介します。
以下は逐次的翻訳文ではなく、私の読後感も交えた抜粋文です。
典夫はある時例によって運転中に何かを考えている時、様々な考えが起きては去って行くのを見ていた。考えが湧いてきて去った後、次の考えが湧いてくるまでにほんのわずかだが、何もない静寂があるということに気づいた。考えが湧いてくる前にも後にも間隙があったのだ。あたかも静寂と言う生地があってその上に思考が乗っているような感じだった。思考の間隙はほんのわずかの時間だったが、非常に興味を引かれた典夫は間隙の方に注意を向けた。その体験があった後のこと。
やはり運転中、陽光と空の美しい自然の驚異に満ちた風景の中を走っていたのだが、景色よりももっと気をとられていたことは思考というものと、あの静寂の瞬間の発見と言うことだった。そして静寂というものの不可思議さについて夢中になって思索していた時のこと。静寂の間隙がほんの一瞬の長さから何分の一秒、そして一秒、二秒、数秒となり、しまいに十秒、十五秒の長さになっていったのだった。その静寂の時にあらゆる思考は消え去り、彼のマインドは完全に静かになった。それにも関わらず周囲の状況は把握できていたし、運転は完璧に制御できていて道路の状況や他の自動車も見えていた。何も考えていない時のほうがかえって周囲の状況がクリアに把握できていることから、思考はむしろ邪魔なのだと思えた。典夫という人物が運転の主導権を握っているのではなく、典夫は単なる代行者なのだと思い、自然に動いて行く流れに楽について行くだけにして、思索作業に戻った。思考と静寂の二つは正反対の現象であり、静寂という間が無かったら思考は出てくることはできないという意味で補完関係にあるのではないか。しかし、思考は時間的に有限であり、消えてゆくのに対し、静寂は永遠で時間を超越しているものなのだと考えていた。
今や静寂は分単位になり、思考にとって代わった。静寂の支配する中は空白でありながら、同時に何かが充満していて、形はなく、内容物はないのにも関わらず、そこに満ちている存在はそれが何であるか説明不能のものだった。神の恩寵と呼ぶか、絶対平等性と呼ぶか、無償の愛と呼ぶか、他にもいろいろの表現はあると思うがどれもそれを表現するには十分ではなかった。そして、今までにそこに行ったという記憶はないのに、まるで故郷か自分の家に帰ったような感じがした。
サービスエリアに車を停め、食堂のカウンターに座り、お茶を飲みながら周囲の人々を見渡すと、キッチンで働く人、カウンターの中の人、何か食べている客がいて、彼も別にその人たちとどこも変わらない普通の人だ。彼にとっての家庭は彼らにとっても家庭だし、彼にとってそうであるものはどの人にとってもそうなのだと思った。誰かが誰かより教養があるとか高学歴だとか能力的に優れているとかは全く関係なく、皆が平等だということに気づいた。全人類共有の場であるパラダイスの真っただ中にあるサービスエリアに、存在の一表象である典夫が座っているのだ。
このことからさらに典夫は運転席から見える風景の中のあらゆる物が、エネルギーの所産であって、それらが生きていることに気づく。生物だけではなく、石や岩までが生きていて、全ては一つなのだと気づいて、最後に角棒で脳天を殴られたかのような衝撃で全身を震わせながら響き渡った声が言ったことは、
ああ、何てこった!僕ってものは本当はいないんだ
僕ってものは存在していないんだ
まだそれは大雑把な気づきだったが、衝撃的な認識であり、粉みじんに打ち砕かれながらも躍り上がるような刺激で、その上非常に滑稽でもあった。
注。このことを The Cosmic Two-by-Four(天からの角棒というような意味)と著者は表現しています。
注。典夫さんは今、自分という個人は幻影であって、実はすべては一つであって、一つしかないのが実在であるという気づきから、個人という幻想を、Phantom Selfと表現しています。
著者は、典夫さんの体験はひとつの体験であって、誰もが同じことをしなさい、それが「気づきへの道」ですとは言っていません。トラックを運転しながら同じような手法を使えという意味ではありません。命とそして宇宙という場を成立、維持、機能させている叡智はただで答を提供してはくれないのです。答は問いに応じて現れてくるものなのです。深遠なる叡智による答を得るには正しい問を持つことなのです。従来のいわゆる人類の智慧の集積が十分ではないばかりかむしろ有害であることは現在の人類社会がどういう状態になっているかを見れば分かることです。人類は今まで種全体としての進化を推進するどころか、何くれとなく策を弄して阻んできたのです。典夫さんの体験はとても面白いものですが、それは典夫さんの物語なのです。それは人というものが本来持っている能力を我々に見せてくれてはいます。喩えとして、豚に羽が生えて飛べるようになるかどうかは可能性としては(絶対ないとは言えない)あっても、豚が本来持っている能力ではないのと同じです。目指すべきものは特殊な例外的個人の気づきではなく、全人類の集合意識の進化なのです。