究極のコトバは光透波、それは実体であって作用ではありません
小田野早秧先生に師事し始めた頃に、光透波理論(当時は命波理論と呼ばれていた)という学問は、古今東西誰も研究したことがないものを研究対象にしていると説明されました。
今まで誰も?インドでもギリシャでも?お釈迦さまも孟子も、プラトンもアリストテレスも、ソクラテスも研究しなかったの?本当に?
人間が毎日の生活でごく当たり前のものとして使っているコトバというものを研究対象にしている学術分野はいろいろあるのではないかと思っていましたので、変なことを言う人だと思ったのを覚えています。
人が使っているコトバ(言語/言葉/ことば)を研究対象にした分野はずばり言語学です。またそこから派生した、言語の使い方、活用や影響力などを研究対象とする分野として心理学、教育学、脳科学などがありますが、あくまでも言語学が基本分野です。
つまり、言語というものの種類やその作用についての研究はされてきたのですが、「言語そのものが何であるか」の研究ではないのです。きっと誰かが既に研究していたのに違いないと思っていたのでこれは全く予想外であり、新発見であり、大きな驚きでした。
では何故これまでコトバそのものが何であるかを体系的に研究した人がいなかったのでしょうか。
学問においては、「〇〇は存在する」ということを証明する際には、どういう形式と構造で、何を材料に、何時できたのか、誰が作ったのか、何処にあるのか等々を調べて行きます。言い換えると存在している「もの」そのもの(それが抽象であれ、具象であれ)を実体[i]とし、その作用[ii]や属性や性質を調べるということになります。
例えば、「愛は存在する」と仮定した場合は愛の作用を調べ、効能や、弊害などの影響力を調べ、影響があったのだから存在すると結論付けるわけです。何故なら愛そのものは触ることも匂いを嗅ぐことも重さを計ることもできないからです。同様に神も悪魔も計測はできません。
先ほどインドでもギリシャでもと言いましたが、今回はギリシャを取り上げて見ましょう。紀元前数百年にギリシャで、プラトンとアリストテレスという二人の賢い人が万物の始原(アルケー[iii])は何であるかを研究しました。
プラトンは、存在する「万物」は先に「イデア[iv]」があって存在する万物はその影であると説きました。
プラトンが『国家』第七巻で記述した洞窟の比喩
地下の洞窟に住んでいる人々を想像してみよう。明かりに向かって洞窟の幅いっぱいの通路が入口まで達している。人々は、子どもの頃から手足も首も縛られていて動くことができず、ずっと洞窟の奥を見ながら、振り返ることもできない。入口のはるか上方に火が燃えていて、人々をうしろから照らしている。つまり、洞窟に住む縛られた人々が見ているのは「実体」の「影」であるが、それを実体だと思い込んでいる。「実体」を運んで行く人々の声が洞窟の奥に反響して、この思い込みは確信に変わる。同じように、われわれが現実に見ているものは、イデアの「影」に過ぎないとプラトンは考えました。
これに対しアリストテレスは師であるプラトンのイデア論を認めようとしませんでした。ものの本質は目に見えないイデアの世界にあるのではなく、そのものの中にこそ存在すると彼は考えました。イデアこそが本質的存在であり、地上に存在する物理的実体はその影にすぎないというのがイデア論の考え方ですが、このイデアなるものは目に見える形で取り出すことができないものであるという点にアリストテレスは納得がいきません。むしろ「実体が先にあって、それらを基にして人間が頭の中で抽象化して創りだしたものをイデアと呼んでいるにすぎないというのが自然な考え方である」というのがアリストテレスの考え方です。
出典:ウイキペディアからの抜粋
さて、両者それぞれのどちらが正しいかはそれぞれの人の根本的なもののとらえ方で決まるだけで正誤の決定要因にはなりません。この前後にも他の学者たちがそれぞれの理論を打ち立ててきました。デモクリトスは、「アルケーはアトム(これ以上小さくできないもの)」である」と言い、ピタゴラスは、「アルケーは数(調和的音階を構成する数)である」と言ったそうです。タレスは「水である」と言い、エンペドクレスは四元素(火、水、土、空気)、ヘラクレイトスは「火」であると言いました。
あなたは「誰派」ですか?
光透波理論的見地から見ると、どの人も「万物の始原」の一側面ないしいくつかの側面を見ていたのです。全部が一部は正解であり、どれもが完全なる説明とはなっていなかったのです。
光透波理論では、「万物の始原」は「光透波」というエネルギーの中でも至高の速度を持つ、唯一の実体、実在であるとしています。そしてそのエネルギーを基本材料として、完全にして狂い無き数の法則に則った構造を持つ形が現象する。それぞれの形が水であり、その水が燃えて現れる火(薪や石油を燃やしてできる火のことではない)であり、冷えた固体である土であり、形を成さないが何もないところを満たして生物を生かしている栄養素・生命エネルギー/プラナを持った空気でもあるのです。空気が含んでいる酸素によって生物は生かされていると多くの科学者が思っていますが、酸素は生命エネルギーそのものではありません。
重要な点として着目して頂きたいことは、ここに列記した「水、火、アトム、数、土、空気」はコトバだということなのです。イデアとはズバリ言ってコトバです。コトバはイメージを持っています。そしてイメージを保有する主体は人間なのです。コトバはまた音を持っています。音は音階を構成します。調和的であれ、なかれ、振動しながら不可視の形を構築しています。想像を絶するスピードで生成されては崩壊し、流転してさまざまな波を起こして周囲に影響をあたえ、干渉し、ある時は同調し、ある時は反発し合って動き続けています。
今までコトバは言語だと思われてきました。言語でもありますが、エネルギーそのもので、究極的には存在(有無)を超越した真空というエネルギーで、万物は真空が核となって回転という動きを可能ならしめられているのです。真空は何もない空白のことではありません。真空が理解できないと万物の始原は分からないのです。小田野早秧が若いころに「真空とは何か」という疑問を持って追及していった結果生まれたのが光透波理論なのです。その真空が核となって回転することで、生み出される波のつくるスパイラルが宇宙本来の美しい形と動きです。その形を調和的な振動で作っているのも歪めているのも人間という存在なのです。コトバを使っている存在を人間と定義した場合という意味においてですが。私は明らかに地球人以外の人と分かる人たちと交流がないので(地球外知的生命体ではないかと思える人には何人か出会いましたが、姿が人間と同じなので確かとは言えません)口幅ったいことは言えませんが、地球外にも人間は存在していると思っています。
万物の始原は光透波であるという仮説を一応立ててから、宇宙の構造を示している幾何図形としてのコトバ、即ち文字というものを様々な角度から検証して行きたいと思います。
以前質問を受けた「水はコトバです」という意味も含めて検証して行こうと思っています。
2017.8.21
[i] 実体=実際にそのものとして存在するもの、本質=永遠に変化せず在り続けるもの。そのものの本当の姿。実質。正体。
[ii] 他のものに力を及ぼして影響を与えること。また、その働き。「太陽熱は植物の生育に作用する」「薬の副作用」「相乗作用」。 二つの物体の間で、一方が他方に加えた力。
[iii] 万物の始原、元となるもの、根源的原理。
[iv] 古代ギリシャ語の動詞「idein」(見る)に由来する。感覚を超えた真実在としての意で用いた概念。英語の「idea」の語源ともなった。
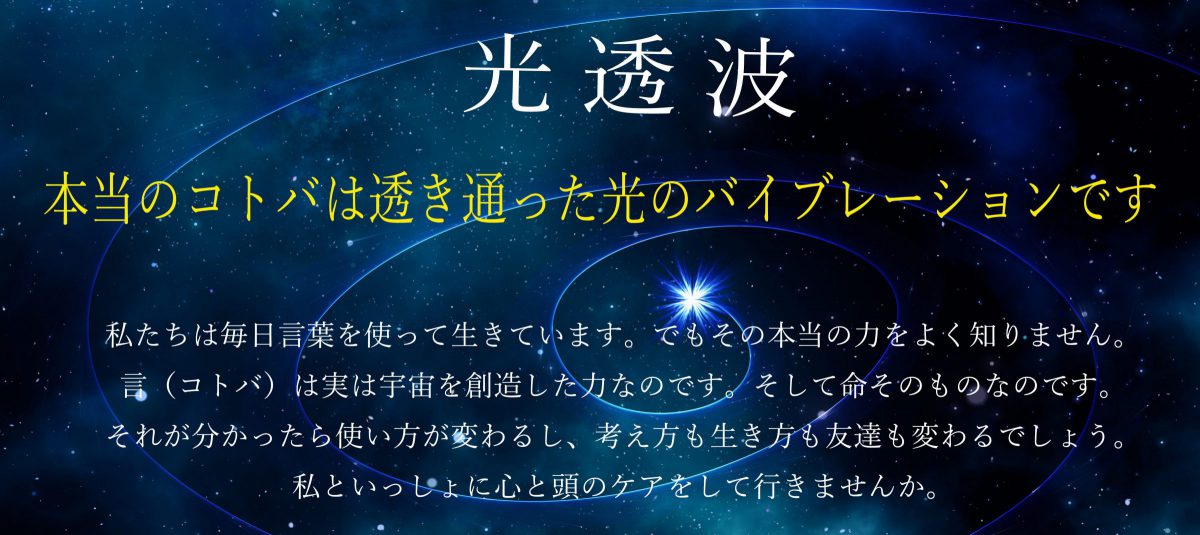

光透波という実体!
昨日、ナシーム・ハラメインさんのhttps://youtu.be/BGGvwkrDZNA
トーラスの中のピラミッド構造が重なり合わさって回転するセンターシステムの動画を見て、「これだ」と思うところがあったのですが、先ほど静流先生のページを開きましたらすっきりと言葉にして下さっていました。ありがとうございます。
水はコトバ、を理解できるように一歩ずつ私なりに考えながら、静流先生のページを追って行きます。